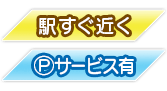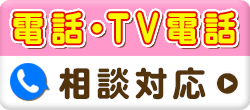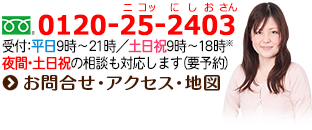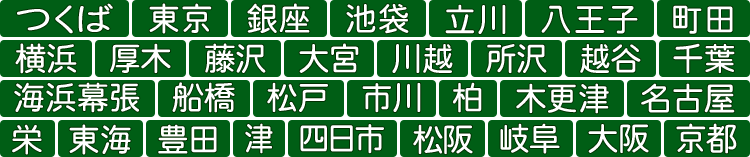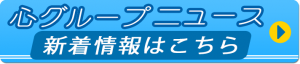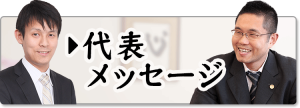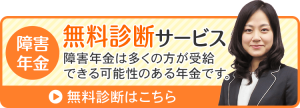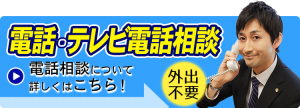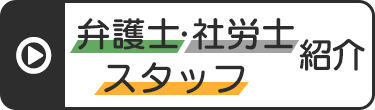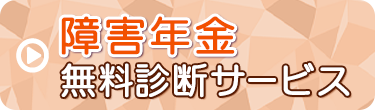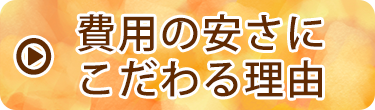脳出血で障害年金がもらえる場合
1 脳出血で障害年金がもらえる場合
脳出血は、一命をとりとめても障害が残ることも多く、その内容も多岐にわたります。
障害年金の対象としては、身体に麻痺が残る場合や、そしゃく・嚥下能力に障害が残る場合、言語障害が残る場合、高次脳機能障害が残る場合があり、それぞれに障害年金が認められるための基準があります。
2 身体に麻痺が残る場合
身体に麻痺が残る場合には、ボタンを閉めたり、スプーン等を使ったり、服を着たり、立ったり、座ったりといった日常の動作にどの程度支障が生じているかどうかが、障害年金が認められるかどうかの判断の分かれ目になります。
具体的には、四肢に麻痺が残った場合には、日常の動作の多くが、一人でできるが非常に不自由な場合に1級、一人でできてもやや不自由な場合には2級とされています。
半身に麻痺が残った場合については、日常の動作の多くが、一人で全くできない場合に1級、一人でできるが非常に不自由な場合に2級、一人でできてもやや不自由な場合には3級とされています。
3 そしゃく・嚥下能力の障害
脳出血によって飲み込みに関連する神経に障害がおこると、のどの筋肉に麻痺が発症することがあります。
このような場合にも障害年金が認められる可能性があります。
具体的には、流動食以外は摂取できない場合や、食事が口からこぼれ出るため、常に手や器具等でそれを防がなければならない等、経口的に食物を摂取することが極めて困難な場合には2級に、全粥等以外は摂取できないものや、経口では十分な栄養が摂取できないためゾンデ栄養の併用が必要な場合には3級とされています。
4 言語障害が残る場合
脳出血によって言語野にダメージを受けると言語能力に障害が生じることがあり、そのような場合も障害年金の対象となります。
具体的には、発声に関わる機能を喪失していたり、日常会話が誰とも成立しなかったりするような場合には2級、話すことや聞いて理解することに多くの制限があるため、日常会話が部分的に成り立つものが3級とされています。
5 高次脳機能障害が残る場合
高次脳機能障害とは、脳にダメージを受けたことにより、注意力や記憶力、言語、感情のコントロールなどがうまく働かなくなる障害のことです。
高次脳機能障害については、日常生活の能力等をもとに障害年金の等級に該当するかどうかを判断していくことになります。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金申請の手続きと流れ
- 障害年金の申請期間
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金における初診日
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の種類
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の納付要件
- 20歳前傷病の障害年金
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- 新型コロナウイルス後遺症と障害年金
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できますか
- ADHDで障害年金を受け取れる場合
- 網膜色素変性症で障害年金を請求する場合のポイント
- 聴力の障害で障害年金が認定される場合
- 脳梗塞で障害年金が受給できる場合
- 脳出血で障害年金がもらえる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 人工関節で障害年金を申請する際のポイント
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- 障害年金と生活保護の関係
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金を受給することのリスクはあるのか
- 障害年金で後悔しやすいケース
- 額改定請求について
- 障害年金の更新に関する注意点
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
0120-25-2403